飲み会やイベントの最後にやる「一丁締め」。あの「いよ〜っ、ポン!」って、なんであんなに全員ピッタリ合うんでしょう?
まず、一本締めと一丁締めの違いについて
よく混同されますが、「一本締め」と「一丁締め」は厳密には異なります。
- 一本締めは「3・3・3・1」の手拍子を一回だけ行うもの(「チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ、チャ!」)。
- 一丁締めは「よーっ、ポン!」と一回だけ手を打つもの。
混同される理由としては、どちらも「締め」の場面で使われ、名称も似ていて区別が曖昧になりがちな点があります。また、地域や団体によって呼称や習慣が混ざって使われることもあり、「一本締め=一回だけ手を打つもの」と誤解されやすいのです。 ここでは、後者の一丁締めについてのお話になります。
結論 日本人は4分の4拍子のとあるパターンを体得しているから
最初に結論ですが、これは分析すると4分の4拍子の1拍目が「ポン」その前の「いよ〜っ」がその前小節の「3、4拍目」であり、アウフタクト(弱起)であるという考え方です。
アウフタクトとは、日本語で「弱起」とも呼ばれ、曲の冒頭が小節の頭(強拍)ではなく、小節の途中(弱拍)から始まることを指します。たとえば「ドレミファソ」の「ド」が拍の途中に置かれ、次の「レ」がで次の小節の一拍目=強拍に入るようなイメージです。曲に推進力や勢いを与える効果があります。
追記ですが、アウフタクト自体は日本人には馴染がありません。これは言語にも現れていて、例えば外国語では英語のAやTheなどの冠詞がアウフタクトにあたりますが、日本語にはそれ無く、実際にアウフタクトのある曲も少ないです。
このパターンを日本人は感覚的に体得しているからであるといえます。
なぜ4分の4拍子なのか
まず、拍子についてです。日本人にとって4分の4拍子自体がとても馴染み深いリズムです。
日本の多くの伝統音楽や民謡、さらに学校教育やポップスなどで親しまれる音楽の多くが4分の4拍子だからです。4分の4拍子(4拍子)はリズムが安定し、身体で感じやすく、行進や踊り、合唱などでも扱いやすいため、子どもの頃から自然に耳にする機会が多く、馴染みやすいとされています。特に明治以降、西洋音楽教育が普及し、行進曲や唱歌に4分の4拍子が多用されたことも背景にあります。
逆にワルツや馬のギャロップと関係が深い西洋的な3/4拍子や行進曲の2/4拍子はちょっと馴染みが無いでしょう。
4分の4拍子の特徴について
4分の4拍子にはある特徴があります。それは「1拍目を強調」「次点で3拍目」ということです。
ここでこの「いよ〜っ、ポン」の一番大事な部分は何でしょうか。
勿論「ポン」です。ここで手拍子を揃え、「締まった」感じを出すというのがポイントなのは言うまでもありません。つまり一番大事な「ポン」は強調されるべき1拍目なのです。
必然的に、前の「いよ〜っ」は前の小節になります。
「いよ〜っ」のリズムについて
この「いよ〜っ」が前小節なのはわかったので、その拍感について考えてみましょう。
4分の4拍子の特徴「3拍目も1拍目の次に強調」に乗っ取ると、表拍が強調されます。つまり1拍目でないとすると3拍目からスタートということになります。
というか、音楽教育を受けていない日本人のリズム感的に1裏拍に合わせるというのはまず不可能です。
そしてこの部分、実は「いよ〜おっ」だったりしませんか?この「お」は4拍目なのです。
無意識のうちに「い」と「お」で既に拍感を揃えているわけです。
実はこのパターン、子どもの頃から「さん、はい〇〇」や「せーのっ、〇〇」で自然に体に染み込んでいるもの。だから「いよ〜っ、ポン!」も何も考えずに完璧に揃っちゃうんですね。
まとめ
日本人が一丁締めをピッタリ揃えられるのは、4分の4拍子というリズムが無意識のうちに身体に染み込んでいるから。「いよ〜っ」で前小節の終わりを感じ取り、1拍目の「ポン!」で決める——まさに日本人ならではのリズム感が生む現象です。こうした小さな文化の中に、日本人の音楽的な素養が隠れているのかもしれません。

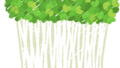

コメント